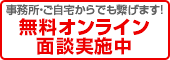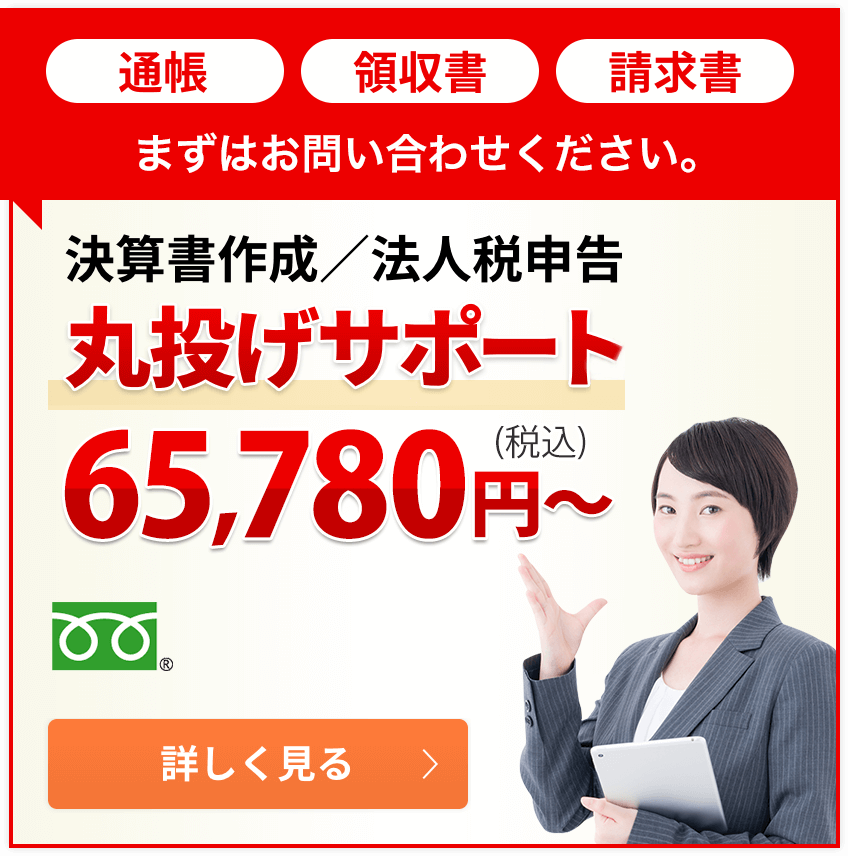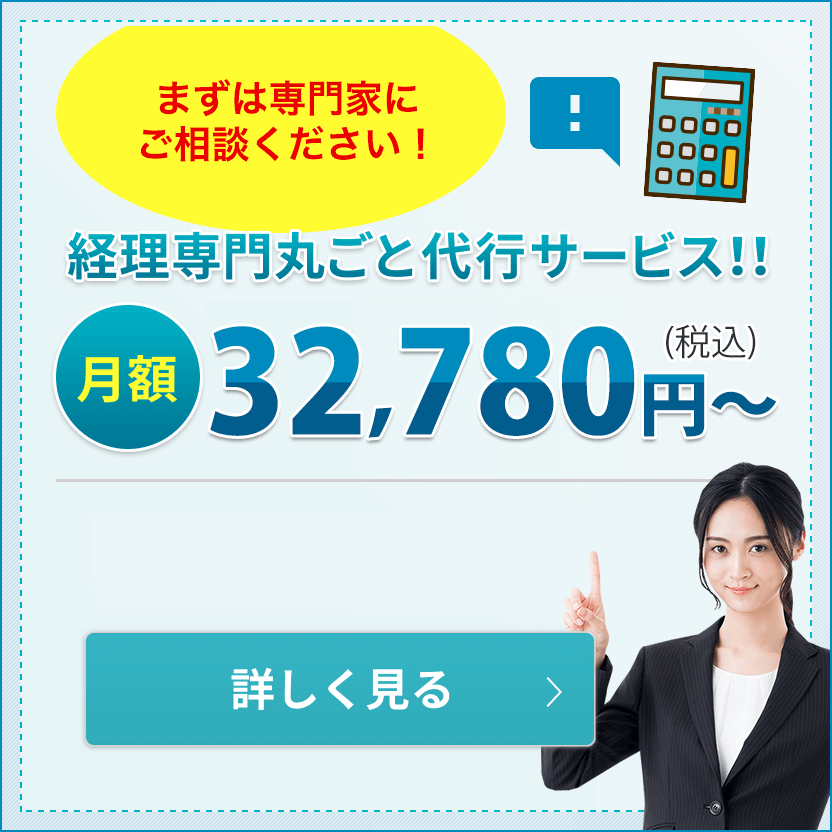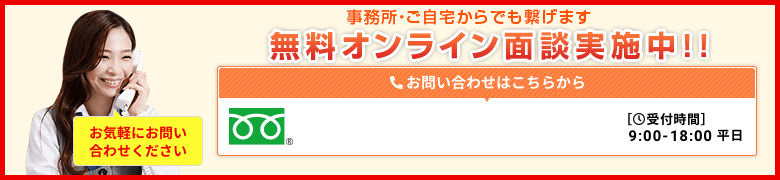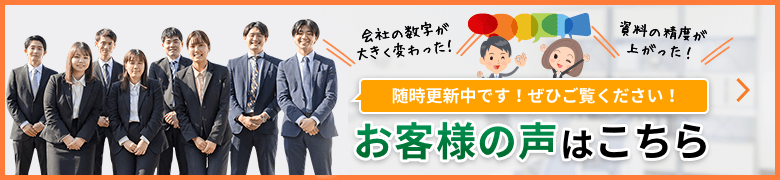【コラム】2023年10月施行!インボイス制度

2023年10月の「インボイス制度」に始まり、2024年1月 「電子帳簿保存法」が施行されます。
今回は、「インボイス制度」と「電子帳簿保存法」について書きたいと思います。
インボイス制度
インボイス制度とは
「インボイス」とは売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝える、適格請求書のことです。
そして「インボイス制度」とは2023年10月から施行される、仕入税額控除の方式です。
インボイス制度が始まるとどう変わる?
インボイス(適格請求書)がなければ仕入税額控除ができません。そのためインボイスをもらえなかったら納める消費税が増えることになります。
インボイス制度への対応
インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
売上先がインボイスを必要とするか検討しましょう。
□課税事業者である売上先➡仕入税額控除のためインボイスが必要
□課税事業者で簡易課税制度を選択している売上先➡インボイスが不要
□消費者や免税事業者である売上先➡インボイスが不要
このような形で事業者によって対応が異なりますので、
しっかりと確認をしたうえで対応を進めていきましょう!
インボイス制度の対応についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせいただくか、
対応の進め方の資料をご用意しておりますので、お手元に保管いただきご確認いただければと思います。
ご案内
大分経理代行センターでは、経理のクラウドツールの導入サービスを実施しています。
クラウド会計は
●一般的な会計ソフトと比較してクラウド会計は安価
●AirレジやSquare等の最新アプリとの連動性に優れている
●場所・端末を選ばずリアルタイムで経営数値を把握可能(複数人同時アクセス可能)
等のメリットがあることから、当社にも実際にクラウド会計について創業期の方を中心にお問い合わせをいただく機会が増えています。
相談は無料!まずはご相談ください